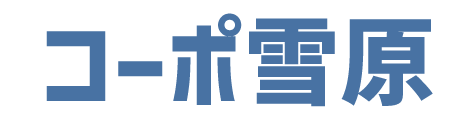加害者
誰だって自己中心的な思考をしているはずだ。自分で自分のことを考えなければ、誰が自分のことを考えてくれるだろうか。だから、自己中心的なことが悪いとはいえないだろう。そこから脱することはおそらく不可能に近いのだから。
しかしそればかりでは、責任転嫁をして難を逃れるズルい人間になってしまうのも事実である。全部他者のせいにすればそりゃ楽だ。だけれども、人生は楽ばかりしてもいられない。
非難されれば、己のプライドを守るために攻撃姿勢に転じる。それはある程度誰だってそうなるものだ。だが、度が過ぎれば取り返しのつかないことになる。
結局のところ、私は無自覚な加害者でした。反省することを拒み、相手に責任転嫁し、全てから逃げおおせようとしていました。
今更、彼から信頼を得ていたことを理解した。
恐怖と被害者意識が加害へのリミッターを外す。わざわざ見えるか見えないかギリギリのところを狙って書き込むのは、傷つけたいという意志があったと言わざるを得ない。そうでなくとも、正々堂々と会話するのではなく、遠回しに伝えようとせんとする態度はズルくて陰湿だ。
その一方で、私の言葉に力はないとも思い込んでいた。実際は助けることもできるし殺すこともできるのだ。しかし活字というのは刺した実感がない。こちらは引き金の冷たさしか知らず、肉にめり込む感触だとか、流れる血の熱さだとか、そういったものは感じ取れない。ゆえにどんな残虐なことでもできてしまう。できてしまったのだ。
きっと私は燃えている。ごうごうと燃えている。けれど、今はまだその熱さの一端しか理解できずにいた。我が事になると、何もわからなくなる。他者の痛みが感じ取れない。自分の痛みも分からない。ただ、分かっていないことだけが分かっていた。
暴力を振るった側は、自分が正しいと思っているから、あるいはそれを暴力だと認める力がないからその行為を忘れてしまうのだ。だから何度でも繰り返す。
恐怖に対する過剰な自己防衛だった。言いたいことは言えず、歪んだ認識と言葉だけが溢れ出た。それは両者を蝕む毒だった。
叱られることは、私にとっては強い恐怖だった。自分のすべてを否定されたように感じてしまう。だから本当に恐ろしかった。
もちろんそんなことはない。あのとき貰った言葉は私の過ちを正すためのもので、否定するための言葉ではなかった。だからこれは、私の認知の歪みに問題があるのだ。
全か無か思考。all or nothing thinking。AでなければB、とは限らない。私を責める者は敵、ではないのだ。むしろ情がなければわざわざ叱ったりはしない。
覆水盆に返らず。放った言葉は無かったことにはできない。後悔しても遅い。必要なのは、本音を相手に伝える勇気だけだった。あんなものは本音でもなんでもない。私は言葉を、ただ相手を傷つけるためだけの道具にしてしまった。
もはや手遅れだった。きっと我々はもう元には戻れない。私が壊してしまったのだ。ただ謝ることしかできなかった。
人の心がわからないのではない。分かりすぎるからこそ、攻撃に転じたときに無自覚な殺戮者となってしまう。そのとき最も有効な手段を選べてしまう。
理解すべきは自己愛の強さだ。自分が大事なあまり、他者をこっぴどく傷つけてしまう。薬の副作用で攻撃的になる、という言い訳もきくかもしれないが、「今の私」はそういう私として生きていくしかなく、私の中にもそういう一面があることを受け入れなければならない。
せいぜい今の私にできることといえば、金輪際同じ過ちを繰り返さないことを誓うだけだ。