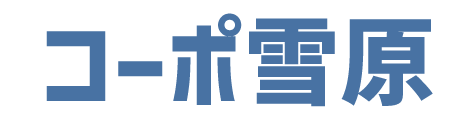病とは
一週間分の薬を、曜日ごとに別れたケースに移し替える。
毎週、その作業をするたび、私はいつまでこのように薬を飲む生活をするのだろうか、と思うのだ。鬱病の寛解とは何を指すのか。いつ減薬が始まるのか。そもそも減らせるのか。先行きが見えない。
ふと、治療を始める前に、薬を飲んだらきっと今の私が消えてしまう、それは恐ろしい、と思っていたことを思い出した。その恐ろしさは、死ぬことすら上回っていた。いや、死ぬことがイコール楽になることだったから、あまり死が恐ろしくなかっただけか。
あの頃は、とにかく全てが不安で、恐ろしかった。不安が消えることにすら恐怖した。だから日記を書き始めたように思える。今の私が消えないように、せめて書き記しておこう、と。その判断は正しかった。あの頃の思考を、気持ちを、きちんと思い出す方法は、日記を読むことだけになってしまった。
そもそも、「病んでいる」とは何を指すのか。それは「生活できるかどうか」だ。鬱の症状は主に憂鬱さと億劫さで、億劫さが強いと生活がままならなくなるので、多くの場合、鬱は「病」とされる。だが、この場合はどうだろう。金銭的に何不自由なくて、世話係を雇えるとする。そうすれば、外に出るのが億劫でも買い物はしてくれるし、飯を作るのが億劫でも食事を作って食べさせてくれる。風呂も介助してくれる。生活が出来ている。ならば、本人が鬱だったとして、本当に「病」と言えるだろうか。
これは発達障害にも言えるだろう。社会が発達障害に理解を示し、本人の能力を引き出せるようになったなら、これは「障害」ではなく「個性」になるはずだ。
だが、とも思う。鬱の場合、憂鬱さはどうなるだろう。毎日気持ちが塞ぎ込んで、常に不安で不安で仕方がなく、死に対して憧れすら抱く日々。それは幸せか。幸せの定義はひとによるのでなんとも言えないが、私はこれを幸せとは呼びたくない。同じように、思ったように日常生活を送れなくて苦しんでいるのなら、やはり発達障害も「障害」なのだろう。
『精神看護学I』には、病むことは、これまでと違った新しい人生を手に入れ、自己成長を得る切っ掛けとなるのである、と記されているらしい。私は、なぜだか、その言葉に反感を覚える。正しいとは思うのだが、感情が、いやそうではない、と言っているのだ。それは、病む以前の私を否定されているように感じるからだ。過去の私だって、紛れもなく「自分」だ。自分を否定されれば、誰だっていい気はしないだろう。
私は、鬱であった頃の私の人格は嫌いではない。むしろ好ましいとさえ思う。だから、「治療」によって人格が変わっていくように感じるのは、やはり今もどこか恐ろしい。不安が消えていくことが恐ろしい。
……いやいや、全く変わっていないじゃないか。序盤に書いたことと同じことを思っている。なんてことはない、何事にも強弱があって、強い不安から弱い不安になっただけだ。なんだ、安心した。
つまり、治療という行為は、己を変えることではなく、己の中の強弱を調節することなのだろう。
先程の言葉に戻る。自己成長を得るきっかけ、これにはやはり納得できない。これは、病を克服したときに成長する、という意味合いだろう。だが、私がこうして文字を書ようになったのは、鬱になったからだ。不安にせき立てられ、手を動かすほかに手段がなかった。できなかったことができるようになることが成長なら、私は克服する前に成長した、ということになる。そして、まるで以前の私が未熟だったから病んでしまったかのようにも聞こえる。いや、事実、未熟だったのかもしれない。過去は未熟で、現在は成熟なのかもしれない。だが、治療の過程で得る変化が全て成熟に、成長に繋がるとは限らない、とも思うのだ。そもそも、何を以て成長と言うのだろうか。社会にとって都合の良い状態を成熟を言うのだろうか。そのときの社会とは何を指すのだろうか。
社会に適応する、という言い回しがある。その状態が、〝人間〟として望ましいと、〝大人〟だとされている。それはつまり、〝人間〟という雛形があり、そこに収まるかどうか、だと私は感じる。
私はその雛形からはみ出した存在だ。故に、「適応」しようともがき、苦しみ、果てに病んでしまった。だから、適応とか、成長とか、そんなものはくそ喰らえ、と言いたい。私は私のままでいいじゃないか。それで離れていく存在がいるのなら、それまでだ。いつか必ず、私を認めてくれる存在と出会えるはずだ。そう信じている。
さて、発達障害や身体障害、性同一性障害などはどうだろう。障害を障害たらしめているのは社会のほうである、とはよく言われるが、全く以てその通りだ。鬱病もまた、社会によって発症「させられた」ものだ。きっと、クィアにクィアという名称が付かなければ、障害という言葉に回収されていただろうな、とも思う。
社会とは、人間と人間との交わりと、経済的な社会とに分けられるだろう。そのどちらもが、〝人間〟とはこうである、という暗黙の了解の元に成り立っている。その定義が狭いから、そこからはみ出した者たちは、病や障害というレッテルを貼られ、仲間ではない、と社会から弾かれてしまう。そこで、はいそうですかと言えれば良いのだが、残念ながら資本主義社会ではそうはいかないことが大半だ。
コミュニケーションは暗黙の了解があってこそ、ということは分かる。例えば、同じ日本語を話すだろうという予測があって、りんごといえば青や緑色の皮で覆われていて、しゃくしゃくとした果実であるという共通の認識がある、といった予測がある。その予測が合っているからこそ、コミュニケーションは成立する。だから、その予測から外れた存在とは会話が成り立たないと直感し、恐れる。
恐怖は無知から発生する。裏を返せば、知れば怖くはない。だから、世の中にはいろいろな存在が居ると知ってほしい。人間であろうと、なかろうと、行動が大多数とはズレていても、それでも仲間になれると、そう思わせてほしい。
そんなことを考えていたら、風呂の栓をしわすれていたらしく、給湯器に怒られてしまった。