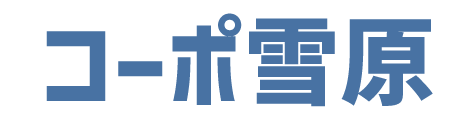君は吸血鬼。僕は、
きっと僕は今、あられもない姿を晒している。
それを取り繕う余裕などなかった。ただ欲望の赴くままに、快楽を欲して、君はそれを与えてくれる。まるで食欲の赴くままに肉を貪る獣のようだ。それは君も同じこと。君の瞳がぎらりと光る。ほら、やっぱり獣だ。
僕の弱いところを君が刺激する。僕の頭の中はからっぽになり、その代わりに、どぎついピンク色のどろどろとしたものが注ぎ込まれる。それは蜜の味であった。
暫く休んだ後、君が再び律動する。そうすると勝手に、僕の息が上がって、赤子のような声が出て、ぽろぽろと涙が出て、体がはねる。全てを起こるがままに受け入れるのは心地が良かった。
僕の口が無意識に、嫌だ嫌だと動けば、君は、嫌じゃあないでしょ、と正してくれる。君はいつも、僕の真実を言い当てる。それが怖くもあり、嬉しくもあった。
既に噛み跡の付いている太ももに、君はまた噛み付く。つぷり、と皮膚が裂ける感覚がした後、君は僕の血を吸う。そうすると、僕の背中にびりびりと電流が流れて、頭上で弾ける。一層、何も考えられなくなる。
君が僕に口付ける。どこか鉄の味がするそれはもう慣れっこになってしまったし、むしろ興奮の材料と化していた。
君は吸血鬼だ。夜に生きて、欲のままに動き、こうして僕の血を吸う。それも、本当に美味しそうに。君が、比喩ではなく、真実吸血鬼であっても構わない。むしろその方が、都合がいい。
僕はどこにも馴染まなかった。常に数センチほど宙に浮いているみたいに不安定で、目立って、そのうちどこにも居場所がなくなった。孤独には慣れていた。だから、どうとも思わなかった。
夜はそんな僕を受け入れてくれた。誰も僕と同じではなかったけれども、それは誰もが同じだった。孤独な僕らは身を寄せ合って、心をあたためあった。人のぬくもりを感じたのは、それが初めてだった。
それでも、腹を見せるのは怖かった。
いつ刺されるかわからない。それならば、鎧を着込んで、それが本当だと偽って、かりそめの安寧が欲しかった。僕にはそれで十分だった。
それでも、君は鎧の隙間に手を入れて、僕の腹に触れた。君の手は熱かった。そして、やわらかかった。君の前では鎧は無意味だな、と思った。だから着るのをやめた。
鎧のない時間は、随分と体が軽かった。
君の前では、本当の笑顔がこぼれる。
僕はすっかり、その感覚の虜になってしまった。
ときどき恐ろしくなる。君を失うときのことを思うと。きっといつか、君は僕の元を去ってしまう。そんな確信があった。そうなってしまったら、僕は孤独に耐えられないだろう。きっと代わりなんていない。唯一無二の存在だから。
僕らはきっと結婚できない。そういった関係ではないからだ。だからといって、友でも、恋人でも、セフレでも、家族でもなかった。僕らの関係性もまた、唯一無二だった。
「ねえ、何考えてるの」
君の視線が、僕の視線と絡まる。
「君がいなくなったときのこと」
「心配しないで。そんなときは来ないから」
うそつき。
君はすぐ嘘をつく。でも、それはいつだって、僕の欲しい嘘だ。だから拒めない。ずるいひとだ。そして、やさしいひとだ。
君が僕に覆い被さる。君の長い髪がカーテンのように垂れ下がって、外界を遮断する。まるで世界にふたりきりになったようだ。
僕は君にそっと口づけをする。そうすれば、君は僕に口づける。僕の中に君が入ってきて蹂躙する。君に暴かれるのは、こわくて、それでいてきもちいい。きっと、君に触れられていない箇所なんて、もうほとんど残っていない。僕はすっかり君のものだ。
君が僕の頬を、体をそっと撫でる。存在していることを確かめるように。輪郭を確かめるように。僕が何者かを確かめるように。
君が吸血鬼なら、僕はきっとゼノ。外から来た者だ。強いて言えば、宇宙人だろうか。それとも深海魚?
どちらでもいいことだった。なんなら、君が何者かすらどうでもよかった。ただ、僕らは今、ここに居る。それだけで十分だった。