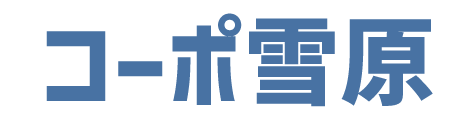とある夕べ
日が落ちた頃を見計らい、緩慢な動きで寝床から這い出る。夜行性の動物にでもなったような心地だが、それは気分だけの話であり、昼行性の生き物が真似事をしているに過ぎないのだ。照明を通電させてやらなければ辺りを見渡すことはできないし、毛布を被らなければ寒さに震えることになる。
人間はいつだってないものねだりだ。夜行性になったらなったで、今度は昼に憧れる羽目になるのだろう。全く難儀なものだ。
我々は欠けている。だからこそ、もしもを夢想し、まさかに怯え、ひょっとしてと希望を抱く。
欠乏感を埋めるように、飴玉をひとつ、口の中に放り込む。甘酸っぱさがじんわりと口内に広がる。恋の味によく喩えられるそれは、切り分けたオレンジのことを言っているのかもしれない、などとぼんやり思う。欠乏感と不安感は隣り合わせか、ごく近くにある気がする。私の感じているこれは、厳密には不安感と形容するほうが正しいだろう。
しかし、不安を溶かすのは時間がかかる。何が原因で、どんな解決策があるのか分からないことだって多い。もっと言えば、そもそも自分は不安なのか、不安ではないのかすら分かっていないこともざらにある。
そういうわけで、その場しのぎに欠乏の埋め合わせを実行してみるというわけだ。戯れに喉の渇きを潤したとて、おそらく私の抱える根本的な渇きの解決にはならないのだろう。真実から目をそらすように、今日も水を胃に落とす。