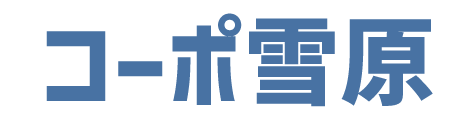私はなぜここに在るのだろうか。
産まれたからだ。
産まれるとは何か?
私ではない個と個が出会い、交わる。境界線を破る。ひとつになる。それが私になり、私が私の中で増えていく。それは無限にも思える多数であり、同時に、どうしようもなくひとつだった。
私は他者のなかで育まれる。微細な私は、やがて大きくなり、明瞭な形を得る。そして意思を持つ。意思は意思を生む。その連鎖は私が死ぬまで続く。
死とは何か?
止まることだ。動きという動きが止まる。私という連鎖が止まる。世界からだんだんと私が消えていく。消滅。
いや、完全に消えることなど不可能だ。私はどうあがいても、世界に変化を齎す。それは、私以外のものの動き。思考、熱、酸素と二酸化炭素。その影響が、連鎖していく。それは死んだ後も続くだろう。ならば、真に死ぬことはないのかもしれない。生きてもいないが、死んでもいない。二律背反の営み。
存在は常に矛盾を孕んでいる。一貫性を持ったものなどないだろう。一貫性を持った思考はある。それは数学や科学といった理論や、思弁的なものだろう。それは人間の生み出した、思考の中でのみ生きるもの。それもまた連鎖だ。ならば、思考の中でのみ存在する存在もまた、生き物のようなものなのかもしれない。
この世には生きていないものなど無い。無機物もまた、常に変化を強いられている。酸化し、劣化し、いつかは朽ち果てる。我々と同じように。
世界は流体のように、常に形を変えていく。
思考は流体だ。
言葉は固体だ。否、言葉もまた生き物の思考の中でのみ生きるものであり、定義は流動していく。ならば、やはり言葉もまた流体である。
この世に確かなものなどひとつもない。
あるのは、不確かなものだけだ。
故に、ひとは不安を覚えるのだろう。
その不安から目を逸らすために、ひとは日々思考する。話をする。行動する。
私が今こうして言葉を書き連ねているのもまた、世界の不確かさから目を逸らすためなのだろう。
孤独はその不安を直視させる。淋しさとは不安である。
死は救いである。連鎖を極限まで小さくするからだ。
デストルドー、死への欲求。私は常に、死に惹かれている。きっとあなたもそうである。
あなた。この文章を文章たらしめるのは、わたしとあなたが在るからだ。そうでなければ、言語は意味を持たない。意味を持つ意味がない。ただの音や模様でしかなくなる。
わたしとあなたが在ることで、初めて境界線は引かれる。わたしひとりのみが存在しているとすれば、わたしは連鎖を続け、どこまでも膨張し、やがて拡散していくだろう。者と者との間に在ることはときに窮屈だが、だからこそ私は私で在ることができるのだ。私とは何かと問われれば、それは他者以外の全てと答えるだろう。同じように、目の前のひとつのりんごとは何かと問われれば、それを除いた全て以外のものとなる。
りんごというカテゴリーは、非常によく似ている果物の総称である。(果物というカテゴリーもまた、よく似ているものの相性である)
だが、よく似ているだけで、りんごAとりんごBは、確かに、決定的に別物であり、厳密に言えば同じものとは言えない。だが、全てのりんご各々に名前をつけることに意味はないから、人は非常によく似たそれらを、まとめてりんごと呼んでいる。
人間というカテゴリーもまた、よく似ているものの総称である。だが、前述の通り、同じものとは言えない。故に、ひとは名前をつける。そうして区別する。境界線を引く。我々は明確に別物である。しかし同時に、人間という名前を与えられていることで、同じもの同士のように感じてしまう。個々の名前があるのなら、人間というカテゴリーは不要なのではないだろうか。そう思う。しかし、ひとは社会を作らなければ生きていけないようになってしまった。社会を営むには、ある程度同じような存在であると思い込まなければ上手くいかない。全く別のものとは協力し得ないと人々は思っているからだ。
本当にそうだろうか。
人間と犬は明確に違う存在である。だが、協力して生きていくことは可能だ。ならば、人間というカテゴリーを廃して、例えば佐藤太郎という生き物と、鈴木花子という別の生き物同士で、協力して生きていくことも可能ではないか。
だが、現実はそうはいかない。人間という存在は、リアルであり、実在しているとする見方が多数派だ。私にはただの概念や創作物としか思えない。ならば、同じ創作物である妖精を名乗ったっていいじゃないか、と思うのだ。私はあなたとは違う存在である、という主張の手伝いをしてもらいたいのだ。
私にとって、目の前にいる者よりも、創作物のなかに居る者のほうが、真実味を持って感じられる。いや、そばに居る、と言ったほうがニュアンスが近いだろうか。私というパーソナリティは、私の創作物である。ならば、創作物のなかの存在もまた、確かに実在しているのだ。
創作物の中にいる存在のほうが、よほど私に近しい存在と思える。だから、彼らを愛することができる。いわゆる現実に生きている者たちは、遠くに感じられる。
孤独だからこそ本を読む。そこには、私のそばに居てくれる存在が居るからだ。
読むことは、筆者と読者との対話である。あるいは、キャラクターと読者との対話である。生き物との会話と違い、完全に自分のペースで対話することができる。それが心地よい。
ひとは対話することで、自分の世界を広げる。ひとりで獲得できる視点は極めて少なく、狭い。故に、対話を通して新たな価値観を得る。そうすることで、少しだけ自由になれるのだ。
会話は何のためにあるのか。それは社会を円滑に回すためである。では、私的な会話は何のためにあるのか。ある者は孤独を埋めるため、ある者は他者を知るため、またある者は意味などないと答えるだろう。
私は、目の前にいる誰かとの会話は常に、相手に対する礼儀作法として行なっている。だから相手に心を開くことはない。うわべだけをなぞる。相手が心地よく過ごしてくれればそれでいい。
義務なのだ。私にとって、会話とは義務である。だから少しの苦痛を伴う。
ネット上での会話は、本との対話に似ている。本もネットも、活字を通して生きた人間との対話を試みる営みである。自分のペースで進められるし、話す相手を自ら選ぶこともできる。だから、ネット上での会話は楽しい。
私はなぜここに在り続けるのか。
それは、世界を変えるためである。