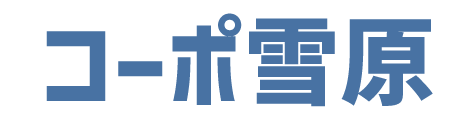眩しくて思わず目を細める。途端に蒸し暑い空気に晒され、一気に汗が噴き出た。
「降谷さんですか」
横から声がしてそちらを見ると、たしかに制服を着た人が立っていた。彼、と言うから男性なのかと思ったが、セミロングの髪を結っている女性だった。少し安心する。
私が、そうです、と返事をすれば、付いてきてくださいと言ってその女性は歩きはじめた。
目の前には、高層ビルが立ち並んでいる。異世界と聞いたから、田舎のような町並みに冒険者が剣を持って歩いていたり、変な生き物が闊歩しているのかと思ったが、案外普通なんだな。これなら安心して歩ける。
私が出てきた場所を見れば、普通のカフェがあるだけだった。彼女はどうやってお客さんと私とを見分けたんだろうか。
ふと上空を見ると、人が飛んでいて仰天した。箒にまたがって、という訳ではなかった。何も持っていないように見える人から、長くて大きい杖やら、ステッキやら、傘やらさまざまだった。
前言撤回。全く普通ではない。しっかり異世界だ。
「あのう」
「なんでしょうか」
彼女はひどくだるそうな声でそう返事をした。
「いえ、なんでもないです」
「そうですか」
なんというか、触らぬ神に祟りなし、といった感じだ。どこに行くのか訊きたかったのだが、まあ、着けば分かることだろう。
立ち並ぶアパレルショップは、私の普段着のような服を並べている店もあれば、どこかの民族衣装のような服を置いている店もあった。街行く人達は普通の服を着ているように見えるので、あの民族衣装風の服は、もしかすると儀式用か何かなのかもしれない。
——なんて想像を膨らませていると、案内人の彼女はいかにもお役所的な建物に向かっていったので、慌てて後を追った。
中に入ると、やはりお役所らしいこざっぱりした空間だった。
入り口から少し進んだところの床に、魔法陣だろうか、何やら紋様が刻まれている。案内人がその上に立つと、空中に何やら文字が浮かび上がった。
空飛ぶ人間といい、魔法陣といい、異世界然としてきてやや気分が高揚する。しかし同時に、よく出来た仮想空間《バーチャルリアリティ》のようだな、とどこか冷めた気持ちで見ている自分もいた。どうにも現実味がない。そうだ、これは夢なのかもしれない。ならば、急に目覚めてもおかしくはないだろう。たとえ現実だったとしても、異分子としてすぐに帰されるはずだ。なにせ魔法のある世界だ、それくらい造作もないだろう。
そう思うと、急に気持ちが沈んできた。明日からまた会社に行って、やりたくもない仕事で一日が終わって、家では眠るだけの生活に戻るのか。いや、突然仕事に穴を開ければ迷惑になるし、連絡がつかなくなれば同僚も、親も友達も心配するだろう。それは困る。早く帰してもらおう。
二百四十五番の方、十三番窓口までお越しください、というアナウンスが流れる。
「呼ばれました。行ってきてください」
考えている間に受付は済んで、更に呼び出されたようだ。役所といえば待たされる印象があるから拍子抜けした。
「早速ですが、こちらに手を翳してください」
そう言って受付の人は、何やら、やはり魔法陣の描かれた板のようなものをカウンターに乗せた。私は言われるがままに手をか翳す。そうすると、目の前に、ステータス画面のようなものが現れた。名前、年齢、それから、
──鏡面世界出身?
「これで個人番号の登録は完了しました。以上になります」
「え、以上なんですか?」
「はい」
「あの、帰り方とか、そういうのは」
「それは、こちらでは対応できかねます」
「だから私が来たんですよ、わざわざね。ほら、行きますよ」
例の案内人がいつの間にか後ろに立っていた。
「行くって、どこにですか! それに、登録ってなんなんですか! 帰れるんじゃないんですか!」
案内人は顔を顰め、うるさいなあと漏らす。
「せめて質問は一個に絞ってくださいよ。それに私は、質問に答える義理なんてないです」
「な、なんですかその言い草は! こっちは不安で仕方がないんですよ。少しは優しくしてくれてもいいじゃないですか!」
不親切な案内人は、はあと大きな溜息を吐いた後、実にだるそうに口を開いた。
「一、これから私の勤める会社の分駐所に行きます。二、それは個人番号の登録。三、あなたは帰れない。以上。あとは黙って付いてきてください」
今、帰れないと言った?
言いたいことは山ほどあったが、仏頂面の彼女に訊く気にはもはやならなかったし、こんなところで口論をしてもしょうがない。私は渋々、黙って付いていくことにした。
少し歩いて、バス停の看板が立っている場所で立ち止まった。看板と言っても、電光掲示板のようなものが付いており、あと何分でどこそこ行きのバスが到着する、と表示されている。ハイテクだ。
イギリスを思わせる二階建てのバスがやってきた。よく見ると車輪がなく、宙に浮いており、まるで空飛ぶ箱である。
後ろのドアから乗り込む。なんだか電車みたいだ。
——気まずい。
仏頂面の人と隣り合わせで黙って座るのは、非常に気まずい。
しかし、今逃げ出しても、一文無しのうえに土地勘もないのだから、すぐ路頭に迷っておしまいだ。仕方がない。仕方がないんだ。そう己に言い聞かせるしかなかった。
窓の外に視線を向ける。知らない街並みが続く。
だんだん心細くなってきた。急に、テーマパークで迷子になったときのことを思い出した。きらきらして見えた場所が、突然怖い場所になる。周りは誰も知らない人ばかりで、頼ることはできない。どこに行けばいいのかも分からない。
あ、だめだ。泣きそう。もう大人なのに。
「降りますよ」
思わずびくりと体が跳ねた。ようやくこの空間から解放されるらしい。
バスから降りると、そこには少し古く見える雑居ビルが立ち並んでいた。そのうちの、いつだか見学した、昔のアールデコ調の建物を思わせる造りをしたビルに入る。
中はひんやりとしており、外の暑さを忘れさせた。コンクリートの階段には、少し煤けた赤い絨毯が敷かれている。なんだかレッドカーペットみたいだ。
四階のある扉の前で立ち止まる。
「入ってください。私はこれで失礼します」
そう言って仏頂面の案内人は去っていった。