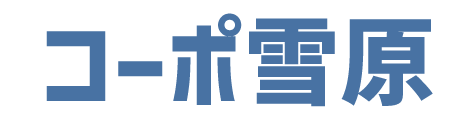意識が浮上する。
目を開ければ、木製の天井が見えた。
ここはどこだろう。
身を起こすと、私はベッドに寝かされていたことが分かった。
視線を落とすと、知らない服を着ていることに気がつく。病院の服ではないから、搬送された訳ではなさそうだ。
ならば、攫われた?
まさか。私のような、平々凡々とした女を攫って何になる。いや、臓器売買という線もあるか。しかし、それにしては丁重な扱いである。ならば、記憶にないだけで、倒れたところを助けてもらったのかもしれない。しかし、そんな急に記憶をなくすことなんてあるか。あるだろうな。
何事も、ありえないなんてことはありえない。奇跡は、起こった瞬間に奇跡ではなくなるように。
とりあえず、布団からでるか。
足を下ろせば、そこにはご丁寧にスリッパが用意されていた。ありがたく使わせてもらおう。
ドアを開ける。
リビングらしき場所に出た。
一見、こぢんまりしているが、手入れの行き届いているのはたしかだ。家具一点一点も上品である。柔かそうなソファに、ローテーブル。チェストの上には雑貨と花瓶。なにかしらの花が生けられている。窓からは燦々と陽の光が差し込んでいる。
暫くきょろきょろと辺りを見渡していると、目の前の扉が開かれた。
「まあ!」
まばゆいばかりに陽の光を反射するブロンドヘアの女性が駆け寄ってくる。髪はとても長さがあり、三つ編みにしているが、おそらく、解けば身長よりも丈があるんじゃないだろうか。いつか見たアニメーション映画のお姫様を思い出す。
「お体は大丈夫ですか?」
金色の睫毛に縁取られた、ビロード玉のような碧眼。整った鼻筋に、慎ましやかな唇。どこか幼さを残したその顔は、まるでビスクドールのようだ。
「初めて声を聞きましたか?」
「あ、いえ、すみません黙ったままで」
どうやら魅入っていたようだ。
しかし、今の質問は一体なんだろう。
「初めて声を聞くってのはどういうことですか」
「ここにはさまざまな方がいらっしゃるのですが、そのなかに聴覚に障害のある方もいます。ですので、ここで初めて音を聞いたということもあるのですわ」
「はあ……」
ここで初めて音を聞く?
なにかからくりがあるのか。しかしそんな魔法じみたことができるのか。
「立ち話もなんですから、どうぞ、こちらへ」
私はダイニングへと促されたので、付いていく。
「お茶を淹れますから、座っていてくださいね」
そう言って、彼女はキッチンへと向かった。
木製の椅子に腰掛ける。硬い椅子など年単位で座っていないが、この椅子は不思議と体に馴染んだ。
飴色になった肘掛けを思わず撫でる。
「お待たせしました」
彼女の持ってきた明るい色の木製のトレーの上には、硝子で出来たカップとティーポットが乗せられていた。私もこんな丁寧な暮らしを望んだことがあった気がするものの、とうの昔に諦めていた。
「さあ、どうぞ召し上がってください」
目の前に置かれたカップに、琥珀色の液体が注がれていく。
甘い香りが立ち上る。
いただきます、と言ったあと、一口飲めば、ほのかな甘みで腔内が満たされる。渋みは全く感じない。彼女はお茶を淹れるのが上手いらしい。ちなみに私は全然駄目だ。なぜだか、どう頑張っても渋くなってしまう。
「私は山城榛名と申します。よろしくおねがいします」
「私は降谷薫です。こちらこそ、よろしくお願いします」
「素敵なお名前ですわね」
「そうですかね」
こんなこと初めて言われた。まあ、悪い気はしない。
「朝食をご用意いたしますね」
「いや、悪いですよ、助けていただいた上に食事までいただくなんて」
「私がしたいからそうするのですわ。お気になさらず」
そう言われると、なんだか強くは出られない。私は大人しく食事が出来るのを待つことにした。
程なくして運ばれてきたそれは、トーストと何種類かのジャムであった。
「お好きなものを塗って召し上がってください」
「では、遠慮なく」
苺のジャムをさっと塗って齧ると、サクサクとしたパンの耳と、ふわふわしたパン、そして甘酸っぱい苺のバランスが絶妙で、食べる手が止まらなかった。
満腹感でほっこりしていると、彼女は、さて、と言って居住まいを正したので、私もそれに倣った。
「ここは降谷さんの居た世界とは、似ているけれども違う場所です。あなた方が魔法と呼んでいるものは、物語の話ではなく、本当にあるものなんです。私達はこれを天法と呼んでいるのですが、それはまた別の話ですわね。ええと、そうですね、あとは実際にここから出てみるのが一番かと思いますわ」
「魔法が、本当に?」
「ええ。例えば、こうして」
彼女が私のカップに手を翳すと、絵の具を垂らしたように色が黒へと変化した。
ありえないことはありえないと思っていたが、これはさすがにありえないんじゃないか? いや、現にありえているんだけども──などと考えていると、躊躇していると思われたのか、大丈夫ですよと山城が言った。
「よろしければ、飲んでみてください」
私はおもむろに口をつけた。
「珈琲だ」
思わず感想を漏らすと、山城がふふ、と笑った。
私はそんなに素っ頓狂な顔をしていたのだろうか。少し恥ずかしくなる。
あ、と急に山城が声を出す。
「すみません、勝手に着替えさせてしまって」
そう言って彼女は申し訳なさそうな顔をした。
「いえ、気にしないでください。むしろ着心地が良くてありがたいくらいです」
「よかった。それはなによりですわ」
突然、ジリリリと古風な着信音が鳴り響く。彼女は、もう、せっかちですこと、と言いながら席を立った。
「すみません、少々席を外しますね」
「はい」
そういえば、私のスマホはどうなっただろうか。画面をつけてみる。圏外。そりゃあ異世界らしいから当然か。
珈琲を飲み干した頃、彼女は帰って来た。
「慌ただしくて申し訳ないのですが、あなたを呼んでいる方がいらっしゃるので、外出する支度をして頂いてもよろしいでしょうか。お洋服はあなたの寝ていらっしゃった客間にございますので」
「わ、わかりました」
部屋に戻れば、確かに私の服がきれいに畳まれていた。
いつもの服に袖を通すと、なんだか妙に懐かしい気持ちが湧いたあと、元の世界に戻ったようで少し気が滅入った。
着替えを済ませて部屋から出る。
「行きましょうか」
玄関のドアを開ける。
そこは一面の草原だった。こんなに広いのは初めて見た。一体、何ヘクタールあるんだか。そして、そこここに花壇があり、色とりどりの花が植えられていた。
やや歩いてから振り返ると、今まで居た場所はログハウスだったことが分かった。実に羨ましい。
「きれいな草原ですね。花壇もよく手入れされてる」
思ったままのことを口に出せば、山城は照れくさそうに笑い、ありがとうございますと言った。
暫く山城の後を付いていくと、ぽつんと立っている扉が見えた。思わず猫型ロボットの出すドアを思い出す。
「ここから出ると、警備員の制服を着た案内の人がいらっしゃいますから、その人に付いていってください。彼がいろいろと教えてくださると思いますわ」
てっきり山城が案内してくれるのかと思ったので、私は面食らった。
「山城さんは来てくれないんですか」
「私はここから出られないのです。私が出てしまえば、この空間は崩れてしまうのですわ」
なんだかよく分からないが、とんでもない事情があるらしい。それならば、無理にとは言えない。
しかし、この短時間で随分と山城のことを信頼していたらしい。まあ、よく分からない場所で親切にしてくれたのだから、そうなるのも不思議ではないか。
「それなら、また会いに来ます」
「嬉しい。待っていますわ」
それじゃあまた、と言って、私はドアを開けた。